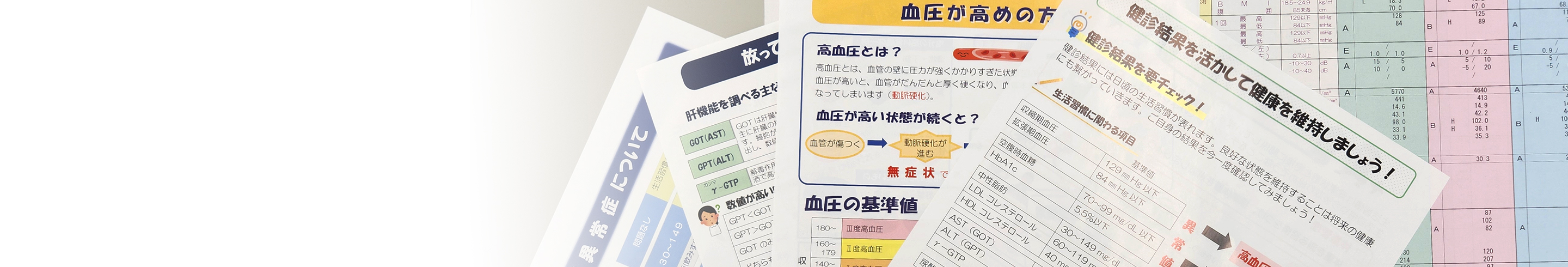
健診後フォロー
- TOP
- 健診後フォロー
-
身体計測
-
-
BMI
BMI=体重(Kg)÷身長(m)÷身長(m)で求められます。肥満や痩せの程度をみるものです。
25以上の肥満は要注意です。肥満になると心肥大や高血圧を引き起こすことがあります。 -
腹囲
へその高さで測る腰の周囲径のことで、内臓脂肪蓄積の指標です。メタボリックシンドロームの診断にも使われます。
-
-
血圧
-
心臓が収縮・拡張した際に、血管(動脈)の内側にかかる強さを表す数値です。動脈硬化のほか、排泄後や緊張・ストレス等によっても上昇します。高いまま放置すると、脳、心臓、腎臓などの病気を引き起こしやすくなります。
家庭血圧を測定しましょう!
- 測定するときのポイント
- イスに座って1~2分後に
- 薄手のシャツは着たままでOK
- カフ(腕帯)は心臓と同じ高さで
-
聴力
-
耳の聞こえを調べる検査です。聞こえにくい場合は、耳や全身の病気の他、騒音や加齢等の影響が考えられます。
-
心電図
-
両手首と両足首、胸元6ヶ所に電極を付けて、体表面から心臓の電気信号を拾い、波形を記録します。心拍数の測定の他、不整脈や心筋の状態などがわかる検査です。
【心電図検査の主な所見】
- 期外収縮
(上室・心室) - 洞結節とは違う場所から早めのタイミングで電気信号が発生することが原因で、通常のリズムではない拍動が出現している状態です。心房で発生した場合「上室期外収縮」、心室の場合「心室期外収縮」と言います。
- 右脚ブロック
(完全・不完全) - 右心室内へ電気信号が伝わりにくい状態を「右脚ブロック」と言います。
- RSR’パターン
- 心室内の電気信号の伝わりに少し時間がかかっている状態ですが、健康な方にも見られることがあります。
- 軸偏位
- 洞結節から発生した電気信号が心臓内を伝わっていく方向のことを電気軸と言います。電気軸が基準よりも右側に傾いている状態を「右軸偏位」、左側に傾いている状態を「左軸偏位」と言います。
- 心房細動
- 左右の心房内で、無秩序な電気信号が発生して細かく震えるように動き、血液を送りだすポンプ機能が低下する不整脈の一種です。心房内で血栓ができやすくなり、脳梗塞を引き起こす可能性がある状態です。
- 洞徐脈
- 1分間の心拍数が50回未満の状態です。スポーツを習慣的に行っている方などにも見られますが、甲状腺機能低下症や心疾患が原因のこともあります。
- 洞頻脈
- 1分間の心拍数が100回以上の状態です。緊張、発熱、重度の貧血などの他に、甲状腺機能亢進症や心疾患が原因のこともあります。
- 期外収縮
-
視力
-
対象となる物の見える力を調べる検査です。視力の低下がみられる場合は、適正な矯正が必要となる場合があります。
-
眼底・眼圧
-
-
眼圧
眼球壁と眼球内を満たしているいい眼内液の圧力です。高いと緑内障の可能性があります。
-
眼底
眼底カメラで、目の奥にある網膜を撮影して、血管・網膜・視神経などをみています。
【眼底検査の主な所見】
- 黄斑変性
- 視力に関係する黄斑の機能が加齢などにより低下する疾患です。視野の中心部が欠ける(暗くなる)などの症状が現れ、視力が徐々に低下していきます。
- 眼底出血
- 網膜の血管が破れて、網膜やその周囲に出血が起こっている状態です。糖尿病や高血圧症などの全身性の病気が原因になっていることもあります。
- 視神経乳頭陥凹拡大
- 視神経乳頭部には、くぼみ(陥凹/かんおう)があるため、緑内障などで眼圧が高くなってくると陥凹が拡大してきます。視神経乳頭の形状には個人差があるため、生まれつきや強度近視などでも陥凹拡大に見える場合があります。
- 網膜前膜
(黄斑上膜) - 網膜の表面に、線維のような薄い膜が付着した状態で、この薄い膜が時間の経過とともに収縮すると、網膜にゆがみが生じます。視力低下や物がゆがんで見えるなどの症状が現れます。
-
-
肺機能検査
-
肺の換気機能を調べる検査で、肺活量、%肺活量、1秒率などを測ります。気管や肺に異常がある場合は異常を示します。
-
胸部X線・喀痰検査
-
-
胸部X線
肺の病気(肺がん、肺結核、肺炎など)や心臓肥大などの心臓の状態あるいは横隔膜の状態について検査します。
【胸部X線検査の主な所見】
- 胸膜肥厚
- 肺を包む胸膜が厚くなった状態です。過去の胸膜炎、肺感染症などが考えられます。
- 線状・索状影
- 線のように見える陰影で、やや太い陰影を索状影と呼びます。炎症の後によく認められます。
- ブラまたは嚢胞影
- 肺胞の壁の破壊や拡張によって、隣接する肺胞と融合した大きな袋になったもので、一般に直径1cm以上のものを言います。これが破れると自然気胸という病気が起こります。
- 石灰化影
- カルシウム成分が沈着した陰影です。結核などの古い炎症の後によく認められます。
- 心陰影の拡大
- 心臓の陰影の幅が胸の50%よりも大きくなっています。肥満、心不全、心臓弁膜症などの場合に見られます。
-
喀痰(細胞診)
顕微鏡で痰を観察し、がん細胞が含まれているかを調べる検査です。
-
-
腹部超音波(エコー)検査
-
肝臓、胆道(胆のう・胆管)、膵臓、脾臓、腎臓、腹部大動脈をエコーで観察して、異常所見がないかを調べる検査です。
【腹部超音波検査の主な所見】
-
のう胞
- 肝臓・腎臓・脾臓・膵臓などに液体を含む袋(嚢胞)ができた状態で、単発あるいは多発することがあります。通常は無症状ですが、大きくなると膨満感や圧迫感等を感じることがあります。膵嚢胞は他の部位にできる嚢胞とは違い、膵臓がんなどの病気が隠れている場合があるため、5㎜以上のものは精密検査の対象になります。
-
肝臓
- 脂肪肝
- 肝細胞に中性脂肪が蓄積した状態です。自覚症状はほとんどありませんが、進行すると脂肪性肝炎になり、肝硬変や肝臓がんになるリスクが高まるといわれています。
- 肝血管腫
- 肝臓に発生する良性病変です。ほとんどが無症状で人間ドックなどで偶然発見されることが多い所見です。血管の塊のようなものですが、エコーで他の腫瘤と区別が困難な場合は、精密検査が必要になる場合もあります。
-
胆のう
- 胆のうポリープ
- 胆のう内腔の粘膜の盛り上がり像を胆のうポリープと言います。そのほとんどが良性のコレステロールポリープですが、10㎜を超えるものや増大傾向のあるもの、小さくても形状が異常なものはがんなどとの区別が必要になります。
- 胆のう結石
- 結石のサイズや個数に関わらず、経過観察が一般的ですが、胆のう内の大部分を結石が占めているとエコーでは胆のう壁の観察が困難な場合がありますのでその場合は「胆のう壁評価不良」として精密検査の対象となります。
- 胆のう腺筋腫症
- 胆のう壁が肥厚する良性疾患です。無症状で経過観察が一般的ですが、胆のう腺筋腫症の特徴がエコーではっきりしない場合は、胆のうがんとの区別が必要になるため精密検査の対象となります。
-
膵臓
- 膵管拡張
- 消化液である膵液は膵臓で作られ、膵管を通って十二指腸に流れます。この流れが妨げられると上流側の膵管が太くなります。原因として膵石や腫瘍が考えられますのでどんな原因で太くなっているのかを調べる必要があります。精密検査を受けて下さい。
-
脾臓
- 副脾
- 脾臓の近くに脾臓と同じ組織像をもつ1~2㎝大の腫瘤のことを副脾と呼びます。病的な意義はなく特に治療の必要もありません。
- 脾臓腫大
- 脾臓の最大径が10㎝以上の場合を腫大としており、15㎝以上で精密検査の対象となります。腫大の原因は、血液の病気や感染症、肝臓の慢性的な疾患など、脾臓以外の臓器疾患により2次的に起こってる場合が多いといわれています。
-
腎臓
- 腎石灰化
- 腎臓にカルシウムなどの結晶成分が付着した状態です。炎症の痕跡や年齢的な変化の場合が多いとされています。
- 腎臓結石
- 腎臓にできる結石のことです。数ミリ程度の小さいものは経過観察が一般的ですが、10㎜以上の結石は精密検査の対象となります。
-
その他
- 腹部大動脈瘤
- 大動脈瘤の径が45㎜以上の場合は精密検査の対象となります。55㎜以上になると破裂の危険性が高くなるため、緊急的な対応が必要となる所見です。
-
-
診察
-
診察では、医師が聴診、触診で他覚症状の有無を確認します。
聴診は主に肺と心臓の音を聞き、呼吸音に異常がないか、心雑音や心音の不整がないかをチェックします。触診では頸部、鎖骨周りや甲状腺に腫れがないかを確認します。【診察の主な所見】
- 心雑音
- 心雑音の多くは、血液が弁を通る時に生じます。健康な人では心雑音は聴こえないのが普通ですが、『無害性雑音』といって健康な人でも聴かれる心雑音があります。
- 不整脈
- 心臓の拍動する音やリズムが一定でないことです。
- 甲状腺異常
- 甲状腺を触診した際に腫れている場合やしこりがある場合があります。甲状腺の病気が隠れている場合もありますので要精査判定だった場合には甲状腺外来を受診してください。
- 呼吸音異常
- 呼吸運動に伴って、肺や気道から発生する呼吸音の異常です。気管支の狭窄、喘息、肺内に液体があるときや炎症などで聴かれることがあります。
-
血液学
-
-
赤血球 / ヘモグロビン / ヘマトクリット
赤血球中のヘモグロビンは酸素を運搬する重要な役割を担っています。ヘマトクリットは血液中の赤血球濃度を表します。貧血があるとこれらの数値が減少し、逆に多い場合は多血症と言い、血液の流れが悪くなります。
-
白血球
細菌などから身体を守る働きがあります。感染症などの炎症性疾患や白血病などの血液疾患で異常値を示します。喫煙でも増加する場合があります。
-
血小板
血液を固める働きをします。血小板が少ないと出血し易く、多いと血栓ができやすくなります。
-
-
肝・胆・膵・腎機能等
-
-
AST(GOT)/ALT(GOP)
肝臓の細胞の中に含まれている酵素です。肝機能障害がある場合に上昇します。
-
γ-GTP
肝臓の解毒作用に関係する酵素で、特に過度の飲酒によるアルコール性肝障害で値が上昇します。
-
ALP/LDH
肝臓に含まれている酵素です。他の肝臓を調べる検査と合わせて判断します。
-
総ビリルビン
ビリルビンは古くなった赤血球が分解されるときに生成される色素です。肝臓や胆のう・胆道に異常があると、ビリルビンが血液中に増え、黄疸が現れます。
-
総蛋白
蛋白質を合成する肝臓と、排出する腎臓に障害が起こると増減します。栄養不良の際には低下します。
-
アルブミン
肝臓で産生されるたんぱく質です。全身の栄養状態の指標となります。肝障害や排出に関わる腎障害がある場合にも低下します。
-
A/G比
アルブミン(A)とグロブリン(G)との比を表したもので、肝障害・腎障害があるときなどに低下します。
-
血清アミラーゼ
炭水化物を分解する消化酵素で、膵臓から分泌されます。唾液や膵液に含まれ、膵臓、唾液腺の炎症や障害時に上昇します。
-
尿素窒素
食事からとった蛋白質の老廃物の量です。
-
クレアチニン
筋肉の代謝でできる老廃物の量です。腎疾患の他、筋肉量の多い人は高くなりやすい傾向にあります。
-
HBs抗原
B型肝炎の検査です。(+)の場合は、ウイルスを体内に保有しているキャリアの可能性がありますので病院で詳しい検査を受けてください。
-
HBs抗体
(+)の場合は過去にかかったか、ワクチンにより免疫が獲得されたことが考えられます。
-
HCV抗体
C型肝炎の検査です。(+)の場合は現在感染している、もしくは過去に感染していたことが考えられます。(+)の場合は病院で詳しい検査を受けてください。
-
尿酸
蛋白質の一種であるプリン体が代謝される際に生じるものが尿酸で、飲酒や肉食、腎機能障害時に上昇します。
-
-
胃部X線検査(バリウム)
-
造影剤のバリウムを服用し、潰瘍・ポリープや腫瘍などがないかを調べます。
【胃部X線検査の主な所見】
- 粘膜不整
- 胃の内部の壁が乱れている状態です。慢性胃炎や潰瘍、腫瘍などが原因の場合があります。
- ひだ粗大
- 胃粘膜には胃の長軸に沿ってひだが見られますがひだが太くなった状態を言います。
- 透亮像
- 周囲に比べてわずかな造影剤(バリウム)がはじかれた部分が見られる所見です。良性ポリープなどで多く見られ、胃がん(特に早期がん)などでも見られることがあります。
-
胃部内視鏡検査(胃カメラ)
-
鼻や口から内視鏡を入れ、食道・胃・十二指腸の粘膜を直接観察し、潰瘍、ポリープ、腫瘍などの状態を調べます。
【胃部内視鏡検査の主な所見】
- 胃底腺ポリープ
- 胃の上中部にできる1㎝以下の小さな半球状の隆起(ポリープ)です。複数あることが多く良性です。
- 萎縮性胃炎
- 胃粘膜が萎縮し、薄くなった状態です。胃酸の影響を受けやすく、胃潰瘍や胃がんのリスクが高くなります。ピロリ菌の感染または過去の感染が関連していると言われています。
- 胃粘膜下腫瘍
- 胃粘膜の下の層から発生したこぶ状の病変です。良性と悪性があり、精密検査で確認する必要があります。良性と確認できたものは形や大きさの変化を経過観察します。
- びらん性胃炎
- 胃粘膜の上皮が炎症を起こした状態です。一般的にはアルコール、ストレス、薬が原因と言われています。
- バレット食道
- 食道の上皮が胃粘膜の上皮に置き換わった状態です。胃酸の逆流など、長期間食道が胃酸にさらされることが原因で起こります。
- 逆流性食道炎
- 胃酸を含む胃の内容物が食道に逆流することで食道に炎症が生じる病気です。
-
その他の胃の検査
-
-
ヘリコバクターピロリ抗体(HP抗体)
血液を用いてピロリの感染があったかどうかを調べる検査です。
-
ペプシノゲン検査
血液中のペプシノゲンの量を調べることによって、胃の炎症や萎縮の度合いを調べる検査です。
-
胃がんリスク層別化検査(ABC分類)
血液検査でHP抗体とペプシノゲンを測定し、その組み合わせから胃がんリスクを分類し評価します。
-
-
炎症反応
-
-
CRP
身体に炎症があると血液中で増加する蛋白質です。
-
RF
関節リウマチなどリウマチ性疾患を調べる検査で、リウマチが疑われる場合に上昇します。
-
RPR / TPHA
梅毒にかかっているかどうかを調べる検査です。TPHAは1度でも梅毒にかかったことがあると常に陽性を示します。
-
-
尿検査
-
-
尿糖
陽性の場合は糖尿病の可能性があります。
-
尿蛋白
腎臓に障害が起こると、陽性となります。
-
尿潜血
腎臓、尿管、膀胱、尿道、前立腺などの疾患で陽性となります。
-
ケトン体
糖尿病・脱水症状・摂食障害・激しい運動などで陽性となる場合があります。
-
ウロビリノーゲン
正常な結果は(±)で、胆道系の障害で胆汁が排出されない場合は陰性、肝障害で血中のビリルビン値が上昇すると強陽性となります。
-
-
便検査
-
-
便潜血
大腸、直腸、肛門などの消化管からの出血があると(+)になります。痔以外にも大腸がん、ポリープ、憩室など病気の可能性もありますので、(+)の場合は必ず受診してください。
-
-
糖・脂質代謝
-
-
血糖
血液中に含まれるブドウ糖のことです。高値の場合は糖尿病が疑われるのでさらに詳しい検査が必要です。
-
HbA1c
赤血球と血液中のブドウ糖が結合したものです。過去1~2ヶ月間の血糖値の状態を知ることができます。血糖と同様に高値の場合は糖尿病が疑われるため詳しい検査が必要です。
-
総コレステロール
血液中のコレステロール全体を合わせた数値です。
-
HDLコレステロール
善玉コレステロールと呼ばれ、コレステロールを血管壁から運び出す働きがあり、動脈硬化を防ぎます。
-
LDLコレステロール
悪玉コレステロールと呼ばれ、肝臓でつくったコレステロールを体の各細胞に運ぶ働きがあります。過剰になると血管に付着し、動脈硬化を進行させます。
-
non-HDLコレステロール
総コレステロールからHDLコレステロールを引いた数値です。動脈硬化のリスクを高めてしまうコレステロールと言われています。
-
中性脂肪
主に体のエネルギー源となる脂肪の一種です。飲酒・甘いもの・炭水化物の摂り過ぎで高くなります。高い状態が続くと内臓脂肪の増加や脂肪肝の原因となります。
-
-
婦人科
-
-
子宮細胞診
細胞の特徴で以下のように分類されます。
ベセスダシステム※判定は日母分類の結果と合わせて行っています。
【NILM】炎症、非腫瘍性所見
【ASC-US】軽度の扁平上皮内病変疑い
【ASC-H】高度の扁平上皮内病変疑い
【LSIL】軽度異形成、HPV感染
【HSIL】中等度異形成~高度異形成、上皮内がん
【SCC】扁平上皮がん
【その他】腺異型、腺がん
-
HPV
ヒトパピローマウイルスの感染を調べます。「+」の場合、細胞診の結果と合わせて判断する必要があります。
-
経腟超音波検査
膣の中に棒状の機器(プローブ)を入れ、子宮、卵巣などの状態を画像化して調べる検査です。
-
-
乳腺
-
-
乳腺超音波検査
乳腺の超音波検査です。乳房に専用のゼリーを塗って断層面にて乳房内を確認します。
【乳腺超音波検査の主な所見】
- 嚢胞
- 液体が溜まった「ふくろ」のようなもので、1つのこともあれば多発することもあり、大きさも様々です。大きいものでは触診でコリコリとした感じのよく動くしこりとして触れることもあります。自然消滅することも多く、無症状であれば特に心配はありません。
- 腫瘤
- 乳腺とは異なった成分が塊を成していると考えられる超音波像で、良性のものがほとんどです。画像の特徴や過去の画像との比較から悪性の可能性は少ないと判断された場合、経過観察の判定となりますが、超音波検査のみでは判別が難しい場合に精密検査をおすすめすることもあります。
超音波の画像上、腫瘤内に液体部分が混在するものを混合性腫瘤といい、そうでないものを充実性腫瘤と呼びます。
-
マンモグラフィ検査
乳房専用のX線撮影です。乳房を挟んで圧迫して撮影します。
【マンモグラフィ検査の主な所見】
- 構築の乱れ
- 乳腺の歪みや引きつれている状態を言います。手術のあとでもみられます。腫瘤が原因でみられる場合もあり、精密検査が必要となることがあります。
- 腫瘤
- 腫瘤のかたち、陰影の濃度、石灰化や構築の乱れなどの随伴症状とあわせて判定します。精密検査が必要になることがあります。
- 局所的非対象陰影(FAD)
- 乳腺の密度は個人差があり、通常左右差はほとんどないため必ず両方の乳房の画像を比較して調べます。FADは左右の陰影に差が認められる状態で、正常な乳腺のこともありますが病気が疑われるときには精密検査が必要です。
- 石灰化
- カルシウムの沈着などが原因で起こります。良性の線維線腫や異常のない場合でも生じますが、乳がんでも見られる場合があるため、精密検査が必要になることがあります。
-
-
腫瘍マーカー
-
- 主な対象部位
- がん以外で上昇する要因
- 主な診療科
- CEA
- 消化器系(胃・大腸・膵臓・胆道など)のがん、肺がん、乳がん、卵巣がんなど
- 喫煙、加齢など
- 消化器科、婦人科、呼吸器科、乳腺外科
- CA19-9
- 消化器系(胃・大腸・膵臓・胆道など)のがん、肺がん、子宮がん、卵巣がんなど
- 糖尿病、胆石症、婦人科の病気など
- 消化器科、婦人科、呼吸器科
- AFP
- 肝臓がんなど
- 慢性肝炎、肝硬変、妊娠など
- 消化器科
- PSA
- 前立腺がん
- 前立腺肥大、前立腺炎など
- 泌尿器科
- CA15-3
- 乳がんなど
- 肝硬変など
- 乳腺外科
- CA125
- 子宮がん、卵巣がんなど
- 婦人科疾患、月経、妊娠など
- 婦人科
- シフラ
- 肺がん(小細胞がん以外)など
- 肺の炎症性疾患など
- 呼吸器科
- SCC
- 食道がん、肺がん、子宮頸がん、頭頸部のがん、皮膚がんなど
- 皮膚炎、気管支炎、喫煙など
- 呼吸器科、消化器科、婦人科、耳鼻咽喉科、皮膚科
- proGRP
- 肺がん(小細胞がん)
- 肺の炎症性の病気や腎機能障害など
- 呼吸器科、腎臓内科、泌尿器科
-
その他の検査
-
-
頸動脈超音波
頸動脈壁のプラークの状態や狭窄部分の確認ができる検査です。
-
ABI/CAVI
動脈硬化の程度や血管のつまり具合を調べる検査です。動脈硬化が進行すると、狭心症や心筋梗塞、脳梗塞を引き起こします。
-
NT-proBNP
NT-proBNPは、心機能が低下して心臓に負担がかかるほど血液中に多く分泌されます。
この量を調べることによって、心不全の早期発見に役立つと考えられています。
また、NT-proBNPは尿中へ排泄されるため、腎機能低下によっても高値になります。 -
骨密度
足の踵に超音波を当て、骨量を調べる検査です。低下すると骨粗鬆症になり、脊椎の変形や圧迫骨折などの原因となります。
-
FT3/FT4/TSH
甲状腺の機能を調べる検査です。
-
アレルギー検査
アレルギーの原因となりやすい39項目を調べる検査です。
-
LOX-index
脳梗塞、心筋梗塞の将来の発病リスクを調べる検査です。
-
軽度認知障害(MCI)検査
認知症のリスクを調べる検査です。
-
医療機関のご案内
「精密検査・再検査依頼票」がお手元に届いた方は、そちらを持参してお近くの病院またはクリニックへご受診ください。
以下の病院は、当センターの「精密検査・再検査依頼票」で受診ができる病院の一部です。
予約等につきましては受診者様に行っていただいております。必ず受診前に医療機関にお問い合わせください。
- 一部地域医療支援病院もございますが、当センターの精密検査依頼票を持参することで初診時に※選定療養費がかかりません。
- 検査にかかる費用はご本人様負担となりますのでご了承ください。(健保や会社負担のある方は除く)
※選定療養費とは、200床以上ある病院で、紹介状を持参せずに受診した場合に徴収することになっている費用(療養費)のことです。
-
地区
- 医療機関名
- 初診予約
- TEL
-
中央区
- 市立札幌病院
- 可
-
地域連携センター
011-726-7831
予約センター 〈新規受診予約〉
- 斗南病院
- 必須
-
AI電話 平日8:30~17:00
050-1724-6450
- JR札幌病院
- 可
-
地域医療連携センター
011-208-7169
- 札幌厚生病院
- 必須
-
健診後精密検査予約専用〈乳腺・甲状腺・尿潜血以外〉
011-261-6015
WEB(専用予約フォームあり)
- 札幌南三条病院
- 可
-
地域連携室
011-233-3010
初診専用予約
- 札幌南一条病院
- 可
-
初診専用予約(前日まで)
011-271-6050
- NTT東日本札幌病院
- 可
-
入退院・総合相談センター
011-623-8320
- カレス記念病院
- 可
- 愛育病院
- 不要(一部診療科のみ)
-
一部診療科は完全予約/事前にお問い合わせください
代表 011-563-2211
※循環器内科は対応不可
-
東区
- 天使病院
- 可
-
患者サポートセンター/
011-711-1042
WEB(HP上の連絡フォーム)
- 札幌東徳洲会病院
- 不要(一部診療科のみ)
-
一部診療科は完全予約/事前にお問い合わせください
代表 011-722-1110
-
豊平区
- KKR医療センター
- 可
-
二次検診予約専用(平日14~17時)
011-832-3828
- JCHO北海道病院
- 可
-
一部診療科で完全予約制診療科もございますので事前にお問い合わせください。
代表 011-831-5151
※検査項目によって他医療機関の受診を案内させていただく場合がございますので必ずお問い合わせください。
-
白石区
- 北海道がんセンター
- 必須
-
地域医療連携室
011-811-9117
- 恵佑会第2病院
- 可
-
地域医療連携室〈胃部・大腸内視鏡検査など〉
011-863-2111
- 札幌センチュリー病院
- 不要
-
予約なしで受診可(平日のみ)/
代表 011-871-1121
診療科をご確認のうえ、ご受診ください。
- 石橋胃腸病院
- 不要
-
予約なしで受診可
代表 011-872-5811
-
西区
- イムス札幌消化器
中央総合病院 - 不要
胃部内視鏡のみ
予約可 -
予約なしで受診可
代表 011-611-1391
健診後の再検査予約<胃部内視鏡検査のみ>
/WEB予約
- 北海道医療センター
- 不要
-
予約なしで受診可
代表 011-611-8111
- イムス札幌消化器
-
南区
- 札幌真駒内病院
- 必須
-
手稲区
- 手稲渓仁会病院
- 必須
-
予約センター
011-685-2990
-
清田区
- 札幌清田病院
- 不要
-
予約なしで受診可
代表 011-883-6111
-
旭川市
- 旭川厚生病院
- 必須
-
健診後精密検査予約で新患受付とお伝えください
代表 0166-33-7171
〈脂質異常・尿酸・血糖値(HbA1c)・尿蛋白・腎機能以外〉
健康セミナーのご案内
当センターでは、健診をお受けいただいている企業様を対象に、健康セミナーを行っています。
企業様の健康づくりにお役立てください。お気軽にお問い合わせください。
(月~土 9:00~15:00)
保健指導課
セミナー所要時間:60分程度(時間については相談に応じます)
講師:当センター保健師・管理栄養士
料金:22,000円
※別途料金(交通費、資料代等)が発生する場合がございます。詳しくは、お電話にてご確認ください。
※ご依頼は2か月前までにお願いいたします。
- テーマ
- 内容
- 1.今日からできる健康生活
-
・健診結果の見方
・メタボリックシンドロームについて
・高血圧、糖尿病、脂質異常について
・運動、体重管理
- 2.健康な身体は食事から
-
・1日の適正エネルギー量
・バランスのよい食事
・外食、コンビニの上手な利用法
・上手な減塩方法
・カロリー制限の工夫
- 3.たばこと飲酒
-
・たばこやお酒が身体に及ぼす影響
・受動喫煙について
・禁煙の方法について
・お酒の適量、お酒との上手な付き合い方
- 4.がんの早期発見
-
・がん罹患率の現状
・がん検診の受診率
・がん予防の健康習慣
・がん検診の大切さ







